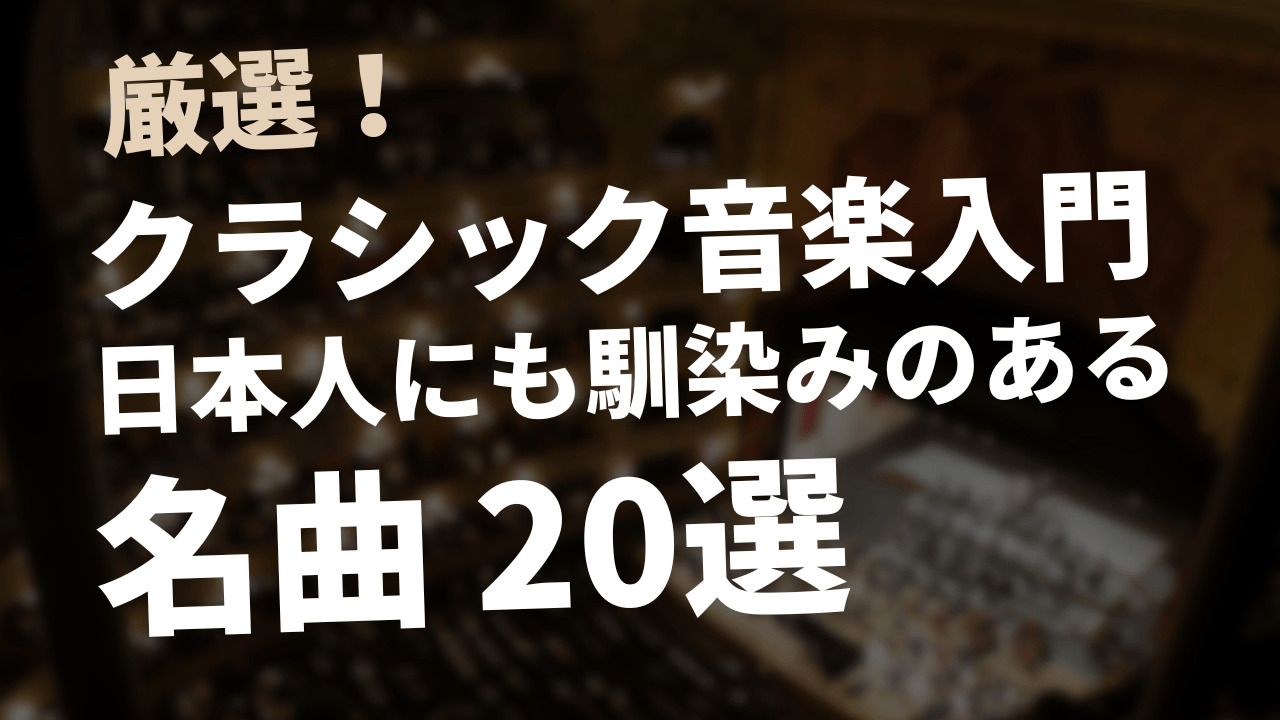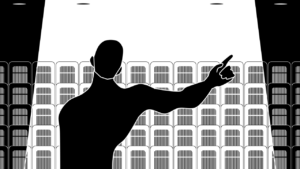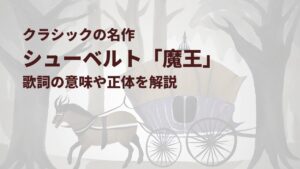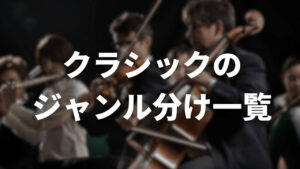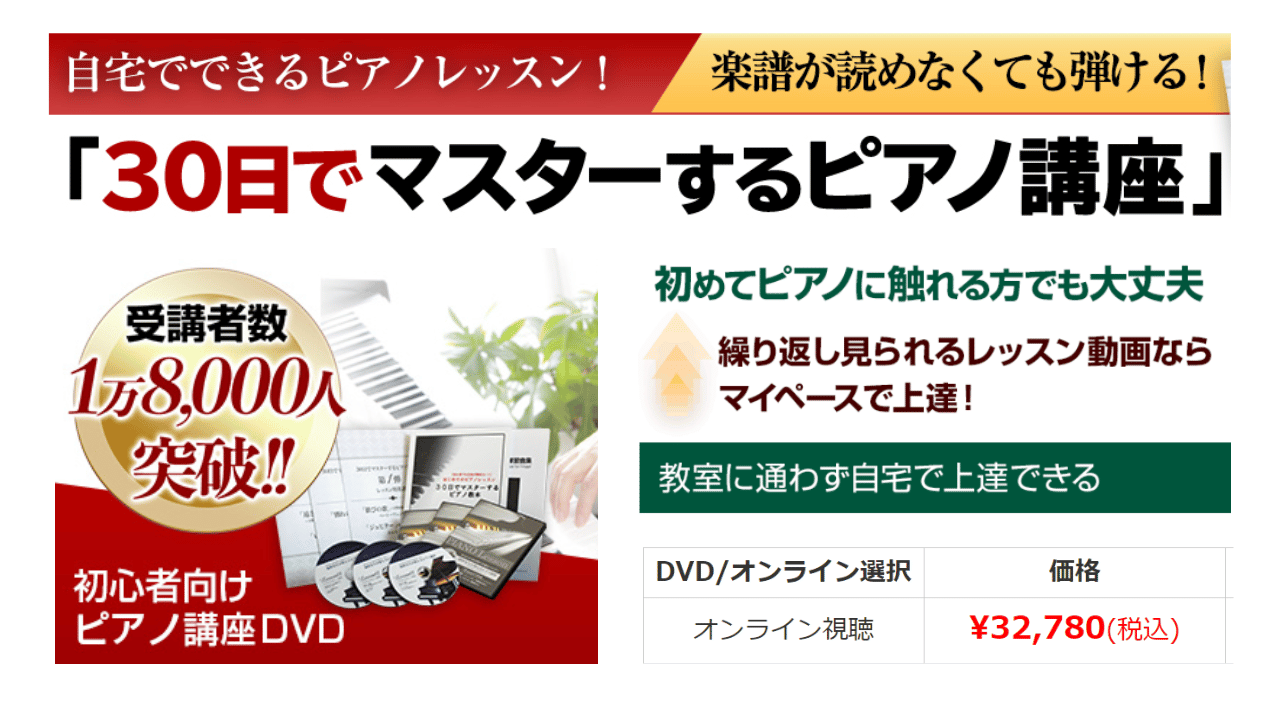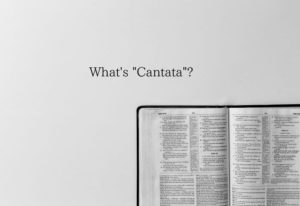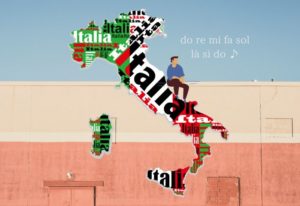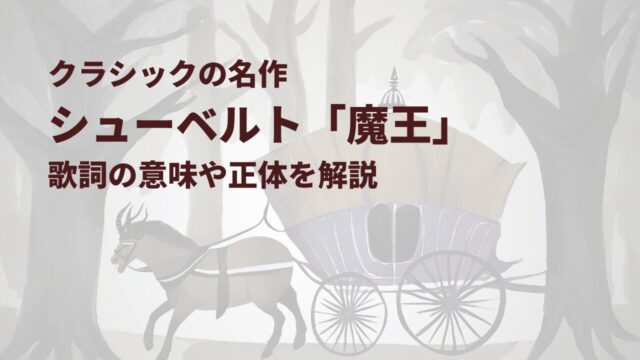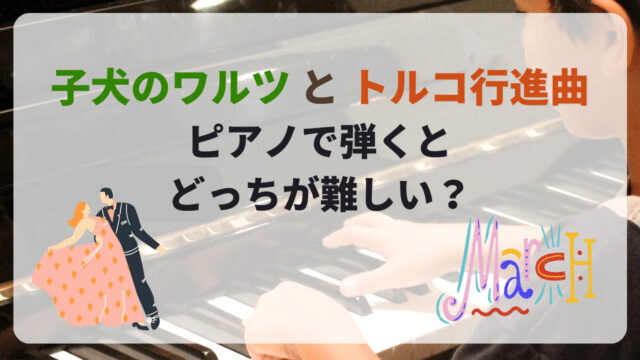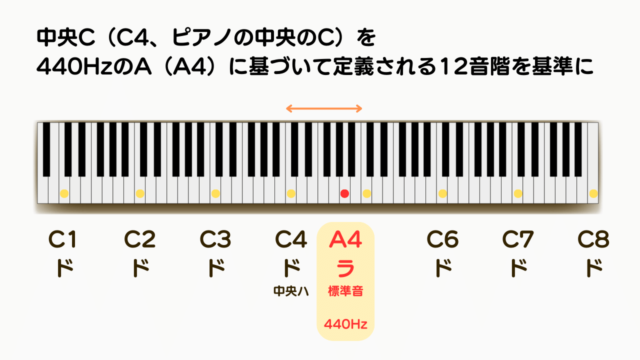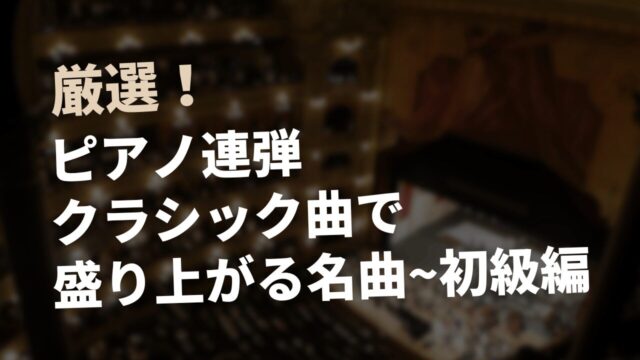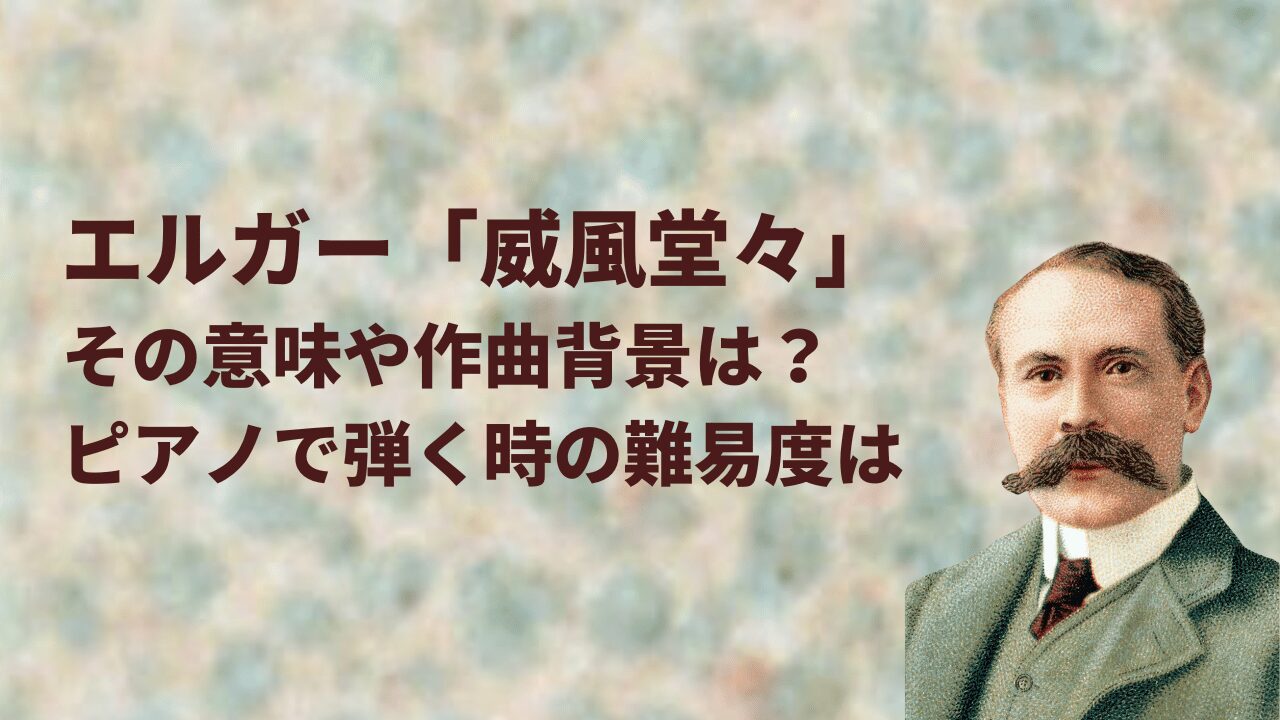
運動会や式典、卒業式などでもおなじみの壮大なメロディ。エルガー作曲「威風堂々」は、クラシック音楽の中でも多くの人に知られ、親しまれている楽曲のひとつです。しかし、その「威風堂々」という言葉には、どのような意味があるのでしょうか。また、原題に込められた意図とはどのようなものだったのか。そして、ピアノでこの名曲を演奏する場合、どれほどの難易度があるのかについても詳しく見ていきます。初心者がこの曲に取り組む際の練習方法も紹介しますので、ぜひ挑戦の参考にしてください。

楽譜が読めなくてもマネするのがピアノが弾けるようになる近道!
おすすめの理由
たくさんの曲が収録されている!
初心者にも弾きやすいようアレンジされた楽譜
繰り返し真似するだけの見放題のレッスン動画
ピアノ教室で高額なレッスン料はなく圧倒的にお得に上達
練習曲リスト
| 番号 | 曲目 | 作者 |
|---|---|---|
| 1 | 第九 歓びの歌 | ベートーヴェン |
| 2 | 組曲惑星より ジュピター | ホルスト |
| 3 | 別れの曲(練習曲作品10の3番より) | ショパン |
| 4 | なごり雪 | 伊勢正三 |
| 5 | 遠き山に日は落ちて(交響曲第9番第2楽章より) | ドヴォルザーク |
| 6 | いい日旅立ち | 谷村新司 |
| 7 | トルコ行進曲 | モーツァルト |
| 8 | 結婚行進曲 | ワーグナー |
| 9 | ガヴォット | ゴセック |
| 10 | クシコスポスト | ネッケ |
| 11 | メヌエット | ベートーヴェン |
| 12 | 主よ人の望みの喜びよ | バッハ |
| 13 | アヴェ・マリア | カッチーニ |
\ さらに今だけラッキー!嬉しい期間限定の特典追加曲付き! /
\ 初心者でも弾ける楽譜を探して購入して、先生を探してレッスン受けに行くのも大変ですから、このレッスン方法は自分のページで必要なものがそろって開始できるので本当におすすめです! /
「威風堂々」の意味と語源
「威風堂々(いふうどうどう)」という言葉は、日本語としては「堂々とした威厳ある様子」「自信と風格に満ちた姿」といった意味で使われます。まさに晴れやかで力強く、誇り高い姿を表す言葉であり、この楽曲の雰囲気にぴったり当てはまる表現といえます。
エルガーの原曲のタイトルは、英語で “Pomp and Circumstance” といいます。これはラテン語由来の表現で、英語圏では「華やかな儀式や見せかけ」「盛大な形式的行事」といった意味を持ちます。シェイクスピアの戯曲『オセロ』の中に登場するセリフ “Pride, pomp and circumstance of glorious war” に由来し、堂々たる行進や戦勝ムードの象徴としてこの表現が用いられました。
つまり「Pomp and Circumstance Marches(威風堂々行進曲)」というタイトルは、「華やかさと格式を備えた行進曲」というニュアンスでつけられており、日本語訳として「威風堂々」と当てたのは、その荘厳で誇り高い印象を的確に表現するうえで非常に優れた翻訳だったと言えるでしょう。この訳語が誰によるものかは明確には記録に残っていませんが、昭和初期にはすでにこの名前で定着していたことから、日本のクラシック翻訳文化の中で自然に根付いたと考えられています。
エルガーと「威風堂々」の背景
作曲者のエドワード・エルガーは、イギリスの作曲家であり、19世紀末から20世紀初頭にかけて活躍しました。「威風堂々」は1901年に第1番が作曲され、後に何曲かがシリーズとして書き加えられていますが、とくに第1番が有名です。この曲の中間部には、イギリスの愛国歌「希望と栄光の国(Land of Hope and Glory)」のメロディが含まれており、英国では愛国的な象徴として広く演奏されています。
エルガーはこの曲を“誇りと気高さ”の象徴として描いたと語っており、決して戦争賛美的な意味合いではなく、人々の尊厳や理想への憧れを音楽で表現したとされています。
ピアノで弾く「威風堂々」の難易度
「威風堂々」は本来オーケストラのために書かれた作品ですが、現在ではさまざまなピアノ編曲が存在します。難易度は編曲によって大きく異なりますが、原曲の迫力を忠実に再現したアレンジでは、左手の和音進行やオクターブ奏法、細かいパッセージなどが含まれるため、中級以上のテクニックが求められます。
音の密度が高い部分や、フォルテッシモの迫力を保ちつつ音程を正確に押さえる場面など、手の大きさや打鍵の安定感も演奏に影響を与えます。さらに、途中でテンポや表情が大きく変わるため、ダイナミクスの調整力や表現力も問われる曲です。
ただし、最近では初心者向けに簡略化されたアレンジも多数出版されており、主要なメロディのみを抜粋したバージョンであれば、バイエル後半からブルグミュラー程度のレベルでも演奏可能です。これらのアレンジでは右手で旋律を、左手で簡単な和音を演奏する構成になっており、発表会の定番曲としても人気です。
初心者が「威風堂々」を練習するためのステップ
まず大切なのは、曲の全体像を理解することです。YouTubeなどでオーケストラ版を繰り返し聴き、曲の構成やメロディの流れ、リズム感をつかみましょう。ピアノアレンジはどうしても音数が少なくなりますが、耳に馴染んだ旋律をイメージしながら練習することで、表現力がぐっと豊かになります。
実際に譜読みを始める際には、メロディラインを片手ずつ練習していくことが効果的です。右手だけ、左手だけでしっかり弾けるようにしてから両手に移ると、スムーズに合わせやすくなります。また、強弱記号を意識しながら、単調な演奏にならないよう工夫することがポイントです。
テンポについては、無理に原曲の速さに合わせる必要はありません。初めはゆっくりと確実に弾き、少しずつテンポを上げていきましょう。また、演奏中の盛り上がりやフレーズの切れ目を意識することで、「堂々とした雰囲気」を出すことができます。
音楽の力強さと品格を、自分の音で表現してみよう
「威風堂々」は、ただ華やかな曲というだけではありません。曲に込められた意味や背景を知り、自分なりにその気高さを音で表現しようとすることで、演奏は大きく変わります。
そして、初心者でも簡略アレンジを活用すれば、この名曲の魅力を十分に感じながら練習することができます。「威風堂々」というタイトルの意味を胸に、自分の演奏にも“堂々とした自信”を持って取り組んでみてください。曲のスケールに励まされながら、ピアノを弾く楽しさを一歩ずつ広げていきましょう。
憧れのピアノが、わずか30日で弾ける!
そんな動画講座のご紹介です
現役ピアノ講師が企画・執筆・制作に携わった初心者のためのピアノ教材。 初心者でも楽しくドレミから学べる内容になっています。これまで楽譜も読めず、楽器を触ったことの無い方でも簡単に理解できるような内容になっています。

憧れのピアノが弾けるようになりました!
ずっとピアノを弾きたいと思っていました。特にソロピアノに憧れていて、みんなが知っているような曲をピアノで弾けたらどんなにかっこいいかと思い続けていました。しかし、教室に通っても短時間のレッスンだと上達する自信がありませんでした。 30日でマスターするピアノ講座は、ピアノを弾くために必要な知識もビデオで学べますし、自分が弾けるようになりたいと思っている曲を先生が弾いてくれるので、その指使いをそのまま真似をして反復練習。 楽譜が読めない私にとっては一番良い練習方法だと思いました。悩むことはなくただ先生の指を真似して同じ音を出すのだと集中して練習に励めるので、30日でピアノが弾けるということも納得です。
- ベートーヴェン作曲「第九 歓びの歌」
- ホルスト作曲「組曲惑星より ジュピター」
- ショパン作曲『別れの曲』(「練習曲」作品10の3番より)
- 伊勢正三作曲『なごり雪』
- ドヴォルザーク作曲『遠き山に日は落ちて』(交響曲第9番第2楽章より)
- 谷村新司作曲『いい日旅立ち』
- トルコ行進曲(モーツァルト)
- 結婚行進曲(ワーグナー)
- ガヴォット(ゴセック)
- クシコスポスト(ネッケ)
- メヌエット(ベートーヴェン)
- 主よ人の望みの喜びよ(バッハ)
- アヴェ・マリア(カッチーニ)
\ 今だけ!嬉しい期間限定特典付き! /
こんなにたくさんの曲を簡単楽譜と動画を見ながら練習できる!